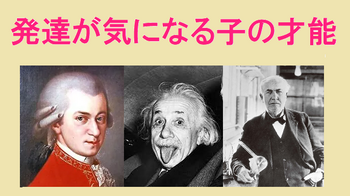発達が気になる子の才能を見つける5つのポイント [教育の小ネタ]
発達障がいの子を天才に育てるスペシャリスト
認知能力トレーナーの内田雄二です。
うちの子の苦手なことばっかり気になって、得意なことなんて見つからない。
そんなお母さん、この動画、必見です!
発達が気になる子の、得意や才能を見つけて育てるポイントが5つあります。
もし、この5つを実践して頂いたら、確実に、その子の未来は開かれると確信しています。
動画はこちら → 才能を見つける5つのポイント
一つ、動画におさめられなかった話をします。
私の小学生の時です。
私は体育が苦手で、特に水泳は水に顔をつけることすらできませんでした。
そこで心配した母は、私を水泳スクールに通わせました。
しかし、私がスクールでビードバンを使って泳ぐとまったく前に進まない(笑)。
そして私の後ろにはいつも長蛇の行列とブーイングの嵐!
つらくって私は家出をし(といっても半日ですが)、水泳をやめました。
次に私は文字を書くのが下手でした。
そこで、母は私を、書道教室に通わせました。
私は何と、半年で2段の腕前に!・・・
でも書道は下手のまま。えつ?
実は、私、お師匠さんの手本を、禁じ手の二度筆を使って、そっくりに偽造できたのです。
それもそのはず、当時の私は絵を描くのが上手で、私の作品が小学校で表彰されたり、教材として永久保存版になっていたのです。
しかし、書道は上達していなかったので、書道大会でお手本がないところに書くように言われて一文字も書けず、泣いて帰ってきました。
そして書道教室もやめました。
母はとても愛情深い人でした。
ただ、才能の育て方を知りませんでした。
苦手なものを困らないように並にしたいと考えました。
でも得意な絵を習わせよう、という発想は皆無だったのです。
こうして偉大なアーティストの誕生が消えました(笑)。
でも、この母の取り組みは無駄ではありませんでした。
この経験のおかげで、私は、教育の道を志すようになったのですから。
人生は不思議です。母に感謝です。
お申し込み後、チャットで、「メルマガ希望」とご送信いただけば、手続き完了です。
<例> メルマガ希望
<ご相談・お問い合わせ>
上郷個別教室GIFTは、発達が気になる子専門の完全個別スタイルの教室です。
認知能力トレーニング、国語・算数の学習支援、SSTを行います。
横浜市高等特別支援学校の受験コースを4月より開講(今年度締め切りました) [教育の小ネタ]
<合格したA君の感想>
横浜市の高等特別支援学校に合格できてうれしいです!
受験対策では、正直、面接練習がとても大変でした。
でも、おかげで本番でスラスラ答えられたので練習しておいて本当に良かったです。
入学したら企業就労できるように頑張りたいと思います。
おめでとう! 今年も上郷個別教室GIFTの生徒が合格しました!
お子さんもお母さんも、今まで一緒に、学科対策、面接対策と頑張ってきた成果です。
入学後も、安心して学校生活を送れるよう、フォローしていきたいです。
また、以前、別の横浜市の高等特別支援学校に合格した生徒も就職活動を頑張っています。
気づけば、本当にお陰様で、受験予備校でもないGIFTですが、今のところ希望した生徒は全員合格してくれています。
本当に有り難いです。
さて、横浜市の高等特別支援学校は大人気で倍率も高く、受験される方も不安ですよね。
そこで、今年は4月より「横浜市高等特別支援学校受験コース」を開講いたします。
<日野中央高等特別支援学校・二つ橋高等特別支援学校 受験希望の方 対象>
今までは、GIFTの生徒達が高等特別支援学校受験を希望してきたために、一緒に受験対策をして応援してきました。
今回はその経験をもとに、初の期間限定で、受験対策希望の方を募集します。
小さな教室ですので、募集は4名まで限定、4月から中3になる子が対象です。
定員が埋まり次第締め切らせて頂きます。 → 締め切りました
お申し込み後、チャットで、「横浜市高等特別支援学校希望 お名前」をご送信いただけば、手続き完了です。その後内田からご返信します。
<例> 横浜市高等特別支援学校希望 〇〇太郎
<ご相談・お問い合わせ>
上郷個別教室GIFTは、発達が気になる子専門の完全個別スタイルの教室です。
認知能力トレーニング、国語・算数の学習支援、SSTを行います。
上郷個別教室GIFT 代表 内田雄二(特別支援教育士)
<所在地> 神奈川県横浜市栄区上郷町1367
<TEL> 045-390-0880
または下記の公式ラインよりお問い合わせください。
トレーニング・学習支援の動画
I have a dream 「僕には夢がある」 ある軽度知的障害の子がくれた勇気の出る言葉 [教育の小ネタ]
今年、高等特別支援学校を卒業し、社会人になる生徒がいます。
彼には大好きな趣味があります。
それはラップ。
聞くのも好きだし、文化祭ではパフォーマーにもなりました。
そんな彼が言った言葉が、すごく素敵でなんです。
これからの発達障がい、知的障がいの子達の、新しい生き方を示しているように感じました。
彼とお母様の許可をもらったので、ぜひ、みなさんと共有したいと思います。
以下、彼の言葉。
「自分はラップと出会って、人生が変わったんです。働きながら、ラップを続けていき、あわよくばデビューしたいと思っています。」
「自分は知的障害じゃないですか。だから、自分がラップという活動を続けて行くときに、知的障害というバックボーンを生かしたいと思っているんです。」
「知的障害である自分が、ラップという活動を続けて行くことで、きっと誰かに勇気を与えることができると思っていて・・・。」
「また、普通のラッパーが呼ばれないようなところで、活動ができるかも知れないと思うし。」
「もしかして、そのうちに、自分のあこがれのラッパーと共演できる日がくるかも」
かっこいい!!!!
これから社会に出るにあたり、不安も多いだろうに、何と希望に満ちてキラキラしていることでしょうか。
人生の主人公として、思い切り人生を楽しもうと思っている。
そして、自分の持つ障害さえも、プラスにとらえ、武器にすらしようとしている。
私、思うんです。
これからの豊かさとは、仕事ができるとか、お金をたくさんもうける、とかが一番ではない。
自分の人生を思い切り楽しみ、幸せに生きること。
それが真の豊かさ!
趣味が人生の1番、仕事が3番以下でいい。
それも、豊かな人生。
彼がこれからの、新しい生き方を示してくれたように感じました。
これからも、彼の最初のファンとして、応援していきたいと思います。
<ご相談・お問い合わせ>
上郷個別教室GIFTは、発達が気になる子専門の完全個別スタイルの教室です。
認知能力トレーニング、国語・算数の学習支援、SSTを行います。
横浜市の高等特別支援学校の受験をご検討の方はこちら
↓